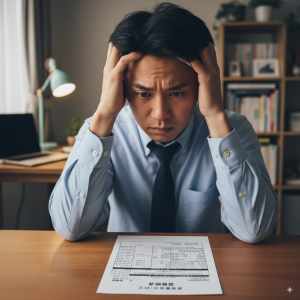おう、俺様、Lo_Guy(ローガイ)のコラムへようこそ。
人事部長なんて肩書きはあるけど、俺の血はギターと同じくらいロックでできてる。今日は「福利厚生」について語るぜ。真面目なテーマに見えるだろ?でもこれが意外とロックなんだ。会社ってステージで社員たちが最高のパフォーマンスを出すためには、PA機材や照明だけじゃなくて、アフターパーティーのケアが必要なんだよ。
ほら、ライブが終わったら打ち上げあるだろ?会社も同じで、本業(給与)以外に「どんな環境やケアがあるか」で、ステージの余韻が決まる。それが福利厚生ってわけだ。
あ、以前も書いたが、利用者によって条件が異なる人事部に関する情報をわかりやすいコラムにするってのはそもそも無理ゲーなんだ。
それをエイヤっと乗り越えるのが、このロックなコラムの存在意義だったりするんだから、あまり細かいところに目くじらを立てるんじゃないぞ。
福利厚生ってなんだ?
まず定義から軽く触れておこう。教科書的に言えば、福利厚生とは「給与以外で会社が社員やその家族の生活を支える制度やサービス」だ。大きく分ければ法定福利厚生と法定外福利厚生がある。
法定福利厚生
社会保険、厚生年金、労災、雇用保険とか、国のルールで決まってるもの。これは「最低限のセットリスト」だ。ライブで言えば定番曲。外したら客が暴動起こすやつ。
法定外福利厚生
会社が独自に用意するやつ。家賃補助とか社食、リモート手当、自己啓発支援、余暇活動サポートなど。これはバンドがオリジナルのアレンジやアンコールで用意するボーナストラック。会社のカラーが出る。
余談だけどな、80年代のHR/HM(ハードロック・ヘヴィメタル)のバンドも、アルバムの「ボーナストラック」で差別化してたんだよ。日本盤だけ追加曲が入ってたりして、ファンはそれ目当てで買ってた。福利厚生もそれに似てる。基本は一緒でも、プラスαで会社に惚れ込むきっかけになるんだ。
福利厚生の歴史をちょっとだけ
昔の日本企業は「社員は家族だ!」なんて言って、やたら手厚い福利厚生を用意してた。社員寮、保養所、家族ぐるみの運動会や旅行。いわば「会社=バンドのファンクラブ」みたいなノリだったんだな。
でも90年代以降の不景気でコストカットの波が押し寄せ、保養所が次々と売却されていった。あの頃は、ちょうどグランジやオルタナが台頭して、華やかな80年代ロックが斜陽になったのと似てるな。
ただ最近はまた潮目が変わってきてる。Z世代やミレニアル世代は「お金だけじゃなくライフスタイル重視」。だから住宅補助やリモート支援、ウェルビーイング施策なんかに注目が集まってる。福利厚生は、再びバンドにとっての“アンコール曲”として大事な位置に戻ってきたってわけだ。
福利厚生のジャンル分け
ちょっとカタログ的に整理してみよう。俺流にロックな比喩を混ぜてな。
生活支援系(ハウジング・フード)
住宅手当、社員寮、社食、カフェ補助 これは「アンプとギターの電源」みたいなもの。なけりゃ音が出ない。
健康・医療系(ウェルビーイング)
健康診断、人間ドック、メンタルケア、ジム補助
ステージで倒れたら終わり。ロックだって体が資本だ。
キャリア・学習系(スキルアップ)
語学学習、資格取得、社内研修、eラーニング
ギタリストが毎日スケール練習するように、社員も成長する環境が必要。
余暇・娯楽系(リフレッシュ)
保養所、旅行補助、ライブ・スポーツ観戦チケット
これはライブ後の打ち上げ。燃え尽き症候群防止の一手。
働き方支援系(フレキシビリティ)
リモートワーク手当、副業容認、時短勤務
ロックの世界で言えば「インディーズ精神」。自由度が高い方がクリエイティブだ。
余談:ロックスターの福利厚生って?
ここでちょっと寄り道だ。ロックスターにも“福利厚生”があったのか?と聞かれると、答えはYESだ。
有名な話だと、ヴァン・ヘイレンが契約書に「楽屋には茶色のM&M’sを置くな」って条件を入れてた。これ、一見ワガママに見えるけど、実は安全管理のチェック用だったんだ。細かい条件まで守られてるかどうかを確認するための仕掛け。つまり福利厚生も同じで、細部のこだわりが全体のクオリティを決めるってことだ。
なぜ福利厚生が重要なのか?
答えはシンプルだ。「人は感情で動く」から。
給与はもちろん大事だけど、それは“チケット代”だ。ライブに行く理由は曲やパフォーマンスだけじゃなく、MCの温かさや、ステージ照明の美しさ、会場の雰囲気だろ?同じように社員は「この会社で働いてよかった」と思える環境を求めてる。
福利厚生はモチベーションを高め、定着率を上げ、採用競争でも強みになる。特に今は「働き手不足」という名の観客争奪戦。差別化できる福利厚生は強力な武器になる。
社員目線でのリアルな声
俺が人事部長として会社の内外で面談をやってると、こんな声をよく聞く。
「在宅勤務が増えたので光熱費や通信費がかさむ。少しでも補助が欲しい」
「子育てと両立できる制度があると安心」
「資格取得を応援してくれると、モチベーションが違う」
「出張の多い職種だから、健康面のサポートがありがたい」
まるでライブで「この曲やって!」ってリクエスト飛んでくるのと同じだな。会社はオーディエンス(社員)の声を拾って、どんなセットリスト(制度)を用意するか考える必要がある。
コストとリターンの話
「でも福利厚生ってお金かかるでしょ?」って声が聞こえてきそうだな。そりゃそうだ。新しい機材を入れるのと同じで投資は必要だ。
ただしROI(投資対効果)を考えると、福利厚生は決して無駄じゃない。離職率の低下、生産性の向上、採用効率の改善。これらは数字で測れる。音楽で言えば、観客動員数やグッズ売上に直結する部分だ。
未来の福利厚生
最後にちょっと未来予想図を描こう。これからの福利厚生は「カスタマイズ」がキーワードになるだろう。
昔は「全員同じTシャツを着ろ!」みたいな画一的なノリだった。でも今は多様性の時代。人によって必要なサポートは違う。
独身者にはスキルアップ支援
子育て世代には時短や保育補助
高齢社員には健康・介護支援
クリエイターには副業容認や在宅環境
つまりフェス型だ。メインステージもあればサブステージもあり、観客が自由に選べる。それが「これからの福利厚生」の形だと俺は思う。
まとめ
福利厚生は、単なるオマケじゃない。社員が長く、楽しく、安心して働けるかどうかを左右する。バンドで言えば、アンコールの出来でライブ全体の評価が決まるようなものだ。
だから俺は言いたい。
「福利厚生は会社のアンコールだ!手を抜くな!」
そして余談だがな、アンコールをケチったバンドはファンにそっぽ向かれる。逆に全力のアンコールをやるバンドは、伝説になる。会社も同じだ。