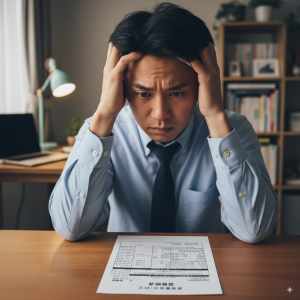ようこそ、ロックな人事部長の人事部へ。
今日は社員の心を最も揺さぶる季節ネタ、「賞与(ボーナス)」について語ろうと思う。
いや、「賞与」と聞くだけでテンションが上がる人もいれば、逆に「少なくてガッカリした」という人もいる。
このテーマ、実は会社の裏側を知るうえで最高にロックなんだ。
なぜって?――「感情」と「数字」が同時にぶつかり合うからさ。
「賞与」は“感情の給与”だが、“原資”は冷徹な数字で動く
まず、最初にぶっちゃけよう。
賞与というのは「給与の延長」ではない。
厳密に言えば、“成果に応じて支払う変動報酬”だ。
つまり、会社が稼いだ利益の一部を分配しているに過ぎない。
じゃあ、どうやってその原資――つまり「賞与ファンド」ってやつが決まるのか?
ここに財務・経理のリアルな視点が入ってくる。多くの会社では、期初(=事業年度のスタート時)に「賞与引当金」という形で“将来のボーナス支払いを見越した会計処理”を行う。
これは「利益が出たら払う」ではなく、「利益を見込んで一部を先に費用として計上する」という会計上のルール。
ただし、この引当の根拠は経営計画に基づくので、景気が悪化したり、利益計画が未達になれば当然調整される。
つまり、賞与ファンドは最初から“確定”しているようで、実は“流動的”な存在なんだ。
賞与ファンドの作り方──“経理”と“人事”の共同作業というバンドセッション
俺の経験上、賞与原資は大きく3つのステップで決まる。
まるでバンドの音作りのように、それぞれのパートが絡み合って曲(制度)になる。
- 経営層・財務パートが「分配可能利益」を算定する。
営業利益・経常利益・純利益……このあたりのどこを基準にするかで会社の性格が出る。
製造業のように在庫を抱える業種では営業利益基準が多く、ベンチャーやIT企業は純利益ベースで判断することが多い。
つまり、「どの利益を源泉にするか」は企業文化そのもの。 - 経理・人事で“ファンド率”を決める。
「営業利益の10%を賞与原資とする」みたいなルールだ。
この数字が経営の覚悟を示す。たとえば10%ならかなり積極的。3%なら保守的。
「会社が利益のどれだけを社員に還元するか」をここで決めるわけだ。
この段階で、俺はよく経理部長と議論になる。
「もう少し社員に報いたい」と俺が言えば、「財務的に持続できる範囲で」と返される。
――つまり、ここが“経営のロックバトル”の舞台なんだ。 - 配分ルールを策定する。
全社業績・部門業績・個人評価。
この3つの要素をどう混ぜるかで、制度のカラーが決まる。
たとえば外資系は「個人評価」比率が高く、日系は「全社・部門業績」寄り。
ここに「組織文化」と「思想」がにじみ出る。
成果主義を掲げながらも、実際は横並びという企業も少なくない。
逆に、スタートアップでは業績が赤でも「未来への報酬」としてボーナスを配るケースすらある。
ロックだろ?
“ロックな”賞与設計──公平と納得感のグルーヴ
さて、このファンドが決まったあとにやってくるのが、「どう配るか」という問題。
これがまた骨が折れる。
社員の数が多ければ多いほど、公平性と納得感の両立が難しくなる。
「なんでAさんが多くて、Bさんが少ないの?」
この質問は、バンドに例えれば「なんでボーカルだけ注目されるの?」と同じ構造だ。
だから俺はこう考える。
賞与制度における“公平”とは、結果ではなくプロセスの透明性だと。
どういう基準で査定し、どんな指標で評価したのか。
それをオープンにすることで、不満の温度を下げられる。ある意味、賞与とは「組織の信頼度テスト」でもある。
制度の裏側を説明できない会社ほど、社員の不満が爆発しやすい。
これはSNS時代の今、致命的だ。
“ブラック企業”のレッテルは、ボーナス支給のたびに生まれる。
賞与における“感情マネジメント”──数字の裏にあるモチベーション曲線
人事部長として、俺がいつも意識しているのは“賞与の効果曲線”だ。
実は、ボーナス額とモチベーションには線形の関係がない。
心理学的に言えば、10万円増えても「うれしさの持続時間」はせいぜい2週間程度。
つまり、「額」よりも「メッセージ」が重要なんだ。
たとえば、同じ金額でも「あなたの努力に感謝します」という言葉と一緒に渡すのと、
無言で口座に振り込むのとでは、受け取る印象がまるで違う。
前者は“ロックな握手”、後者は“無音のトラック”。
だから俺は、支給日には必ず社内放送を入れる。
「みんな、本当にお疲れさま。今期もありがとう!」
――これだけで、空気が変わる。
人は数字よりも“音”で動く生き物なんだ。
ロックと同じさ。
賞与を“投資”に変える視点──成長と報酬をリンクさせる
次に、ちょっと未来志向の話をしよう。
最近では「賞与=成果報酬」から、「賞与=未来への投資」という考え方に進化している企業もある。
たとえば、
- 資格取得や自己研鑽に使うことを推奨する「リスキリング賞与」
- 次期プロジェクト参加に応じた「チャレンジ・ボーナス」
- ESGやサステナビリティ貢献に基づく「社会価値ボーナス」
これらはすべて、“短期の成果”から“長期の価値”へのシフトだ。
俺が思うに、ロックな人事とは「結果を褒めるだけでなく、挑戦を支える仕組みをつくる」こと。
だってロックってのは、“完璧”じゃなく“未完成”を称える文化だからな。
財務視点の“冷静なリフ”──賞与はキャッシュフローの試金石
ここで経理・財務の現実に戻ろう。
賞与支給は、企業のキャッシュフローに直撃する。
いくら損益計算書上では利益が出ていても、現金が足りなければ払えない。
実際、俺が過去に勤めていた中堅メーカーでは、
「賞与月だけ一時的に借入金を増やす」という“ボーナスブリッジ融資”を組んでいた。
笑えない話だが、これが現実だ。
経理部長いわく「資金繰りのピークは6月と12月」。
つまり、ボーナスとは“会社の血流を測るイベント”でもある。
だから、賞与を安定して出せる会社は“財務筋肉が強い”と言える。
逆に、赤字続きでも賞与を出し続ける会社は“覚悟がある”とも言える。
どちらもロックだ。
要は「支払う理由」を持っているかどうか、それが大事なんだ。
変わりゆく時代の賞与制度──固定から可変、そして“物語”へ
今、賞与の形も多様化している。
固定比率型から、完全成果連動型へ。
さらに、最近では“物語型ボーナス”という動きも出てきた。
たとえば、ベンチャー企業では「この賞与は、次の挑戦へのチケットです」と明言する。
額面以上の“意味”を与えることで、社員はそれを「夢の原資」として受け取る。
単なる報酬から、ストーリーの一部になるんだ。
こうした考え方は、Z世代以降には特に響く。
彼らは“金額”よりも“意義”で動く。
「自分の仕事が、何を生み出したか」を共有できる賞与のほうが、長期的にモチベーションを維持できる。
俺はこの潮流を“エモーショナル・キャピタル”と呼んでいる。
ロックな結論──賞与は「約束」ではなく「共鳴」だ
最後に言わせてくれ。
賞与というのは、“会社が社員に支払うお金”ではない。
“会社と社員が、お互いを認め合う証”なんだ。
経理の人間が冷たい顔で数字を弾いていても、その裏には「未来を守るための計算」がある。
人事が悩みながら評価をつけるのも、「誰かの努力を見逃したくない」からだ。
そう、賞与とは経営と社員のジャムセッション。
音がズレても、心が合っていればリズムは戻せる。
ボーナスとは、単なる“金”じゃなく“信頼の音”だ。
たとえ景気が悪くても、支給ゼロでも、誠意を持って説明し、信頼を積み上げていくこと。
それができる会社は、必ず再びグルーヴを取り戻す。
社員のみんなへ。
もし今期の賞与が少なかったとしても、腐るな。
会社は見ている。努力はデータには現れなくても、空気には残る。
そして次のフェーズで、その音が鳴る。
さあ、次のリフを刻もう。
この賞与のリズムが、未来のステージを鳴らすんだ。
Keep on working, keep on rocking.
――ロックな人事部長より。